[対談] イノベーションの視点
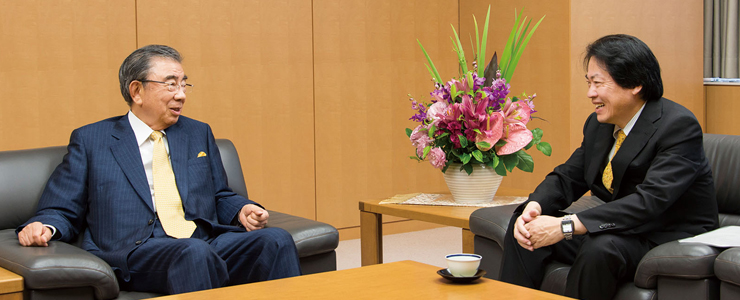
お取引先との信頼関係が新たな市場を切り拓く
野口 日本の消費者が商品を選ぶ目は、ほんとうに繊細です。セブンプレミアムやセブンゴールドは、その日本人の品質に対する感覚を正確にとらえた提案を行い、他との違いを打ち出した商品だと思います。しかも、一つのメーカーに丸ごと商品づくりを委託するのではなく、たとえばカップ麺なら、麺はこのメーカー、具材はこのメーカーと、それぞれのメーカーのもっとも強いところを活かして、ベストミックスによる商品開発を進められています。これは、かつて世界のどの小売業もやったことのない取り組みだと思います。しかも大手NBメーカーが、セブン‐イレブン専用の工場をつくるというのも、かつては考えられなかったことです。
鈴木 それが可能になった前提には、メーカーさんとの信頼関係があります。メーカーさんの高い技術力を活かして、私たちの要望に合った最高品質の商品をつくっていただければ、私たちが確実にそれを売り切っていく、そういう実績を積み上げてきた結果として、信頼関係が生まれてきたと思います。
また、メーカーさんにとって現状では難しいことであっても、それが新しい市場を切り拓く革新につながるととらえていただき、積極的に応えていただけるようになってきました。これもWin -Winの関係を築いてきた成果だと思います。
独自の商品開発を進めれば競合や飽和は起こらない

鈴木 セブン‐イレブンは、創業期から人のマネをしないという考え方を徹底してきました。
今年4月の消費税増税にあたっても、価格訴求に陥らず、他にはない新しい商品を出すようにしてきました。その結果、既存店売上高は消費税増税以降も伸び続けています。
野口 他のコンビニチェーンは消費税増税以降、既存店売上げは前年を下回っていますから、セブン‐イレブンの実績は注目に値します。既存店の平均日販を比較しても、セブン‐イレブンが他のチェーンより10万円以上高いですね。
それだけの差が生まれていると、もはや「コンビニ」とひと括りにして論じることはできません。他社とは次元が異なり、「似て非なるもの」と言っても過言ではないでしょう。
鈴木 私は既存店の売上げが前年を下回るようでは、新店を出していく意味がないと考えています。
野口 デフレ下では、既存店売上げが前年を下回っても仕方がないという大勢の中で、そういう考えで経営されてきたのは希有なことです。
鈴木 ただ、以前と違ってきたのは、天候与件が大きな影響をもたらすようになった点です。かつては、業績の悪さを天候のせいにしてはいけないと言ってきたのですが、最近は天候の影響を無視できません。
野口 近年は異常気象も頻発していますが、消費への影響は小さくないということですか。
鈴木 今年はエルニーニョ現象が起こって、天候不順になるのではと言われています。たとえば、過去のエルニーニョで冷夏となった年と比較すると、今年7〜9月の景気への影響は、家計消費は1・3%から2・3%、GDPは6千億円から1兆数千億円ほど落ち込むという試算が出ています。
また、世界各地で農産物の収穫量が減り、原材料価格が高騰するといった影響も表れます。いまや天候も経済全体に大きな影響を持つようになっています。こうした変化を先読みして、対応していくことが必要です。
ただし、天候はあくまでも予測で、そうなるとは限りません。ですから、グループでは季節商品を準備するとともに、天候不順を想定した商品開発も進め、その影響を最小限にとどめるように指示しています。
