セブン&アイの挑戦
| 2015年7月 |
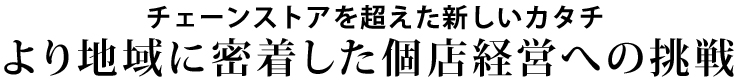
アメリカから日本にもたらされた、チェーンストア理論による大量仕入れ・大量販売の仕組みは、モノ不足の時代にはお客様から支持され、日本の流通の繁栄を支える基盤を築いてきました。しかし、モノ余りの現在、画一的な品揃えでは、一人ひとりのお客様のニーズに応えることができません。そこで、セブン&アイHLDGS.では、 地域性を重視した商品開発や店舗運営に注力しています 。
セブン‐イレブン [ ストア ・ イノベーションプロジェクト ]
「コト発想」から20年後のセブン‐イレブンをつくる
「モノ発想」 から 「コト発想」 へ」

プロジェクトメンバーは、まず外部の情報収集からスタート。ギフトショーをはじめ、さまざまな展示会などに足を運びました。
そういった活動から得たヒントは、「『モノ』ではなく、『コト』から発想してみよう」ということ。
「たとえば、ドリルを買うお客様は、ドリルが欲しいというより、『穴を開けること』が必要なので購入されます。それならば、 他にどういったモノがあれば便利か。そのように生活シーンから発想することで、見えていなかったニーズが見えてきました」とプロジェクトリーダーは語ります。
商圏を調べ尽くしてコト提案

この店舗の商圏の特徴として、後背に住宅立地を持ち、高齢者や女性が多いことがわかりました。そこで、「家飲み需要」が高いと仮説を立て、「お酒のある楽しい食卓」というコトをテーマに売場展開を検討。ワインの種類を増やしたほか、女性に人気のあるフルーツ系リキュールやウイスキーの品揃えを強化。また、おつまみもチーズや生ハム、ピクルス、ドライフルーツなども展開し、「楽しいホームパーティ」を連想させる売場づくりを実現しました。
衆知を集めて売場に活かす
商圏を徹底的に調べ、「コト発想」から今までになかった仮説を立て、実証することで、川崎登戸駅前店は、プロジェクト発足当初、40万円程度だった一日あたりの売上げが、最近は100万円を超える日も出るほどに。「考え方、仕事の仕方を変えることで実績は上がってきました。今後は、他のセブン‐イレブンのお店が、このような手法を採り入れ、『どんな変化にも対応できる発想力』を持って運営できるようお手伝いするのが、私たちの仕事です」とプロジェクトリーダーは抱負を語りました。
セブン‐イレブン [ 地域別マーチャンダイジング ]
西日本MD部関西地区の取り組み
地元に根を下ろしてわかったこと

関西においては、先行して昨年3月、西日本プロジェクトを発足。細やかな地域対応を行ってきました。プロジェクトメンバーが感じたのは、地域独自の食文化があり、今まで推奨してきた商品は、それらの嗜好に合っていないということでした。たとえば、出汁(だし)は関東で好まれるカツオ節を中心に使っていましたが、関西では昆布出汁へのこだわりを強く持っているお店が多かったのです。そこでまず、地元の老舗や商店街に通いつめることから始めました。「そこからさらにわかったのは、それまで『関西』とひと括りに考えていましたが、大阪、京都、兵庫では、味の嗜好もずいぶん違っていたのです」とプロジェクトリーダーは言います。
手応えを感じた「だし巻き玉子」

イトーヨーカドー [ 独立運営店舗 ]
アリオ上尾店の挑戦
「好きなようにやっていい」から始まった模索
イトーヨーカドー アリオ上尾店がオープンしたのは、2013年6月。開業してしばらくは赤字の状態が続きました。そこで昨年1月、「独立運営店舗」として、大きく舵を切ることになりました。経営トップからの指示は、「売上げが半分になってもいいから、好きなことをして構わない」というもの。そこで店長たちが行ったのは、独立運営店舗の先駆けとして成功していたセブン‐イレブン川崎登戸駅前店の視察でした。「品揃えや売り方が、ほかの店とは明らかに違う。我々もほかのイトーヨーカドーとは違う店をつくろうと思いました」と店長は語ります。初めは、「何か特別なことをやらねば」と考えていましたが、一番大切なことはお客様の立場に立って徹底的に考えることだと気づいたのです。
地域に合った品揃え・店づくり

そこで、地元のほうとうやひもかわうどんのほか、香川の讃岐、長崎の五島、秋田の稲庭の3大うどんとそれに合うつゆを併売。ダイナミックな売場づくりがお客様の目を引き、昨年3月以降、うどんの売上げは昨年比110%以上で推移しています。
セルフバーベキューで4カ月、2000万円の効果
独立運営店舗に切り替えてからのアリオ上尾店は、入店客数・売上げとも、好調に推移。売上げは、毎月、昨年比2ケタ伸長を記録しています。
アリオ上尾店の成功を受け、イトーヨーカドーでは昨年12月、独立運営店舗を9店舗に拡大。今年中には全店にこの考え方を採り入れていく予定です。

今までは牛豚鶏それぞれの売場に分散していた内臓肉を、思い切って集約し大きく展開したところ名物コーナーに。バーベキューでも人気。

楽しく食べている様子を撮影し、記念にさしあげるとともに、店内のポスターにも掲載。楽しげな様子が、さらに予約を呼び込んでいます。
- 全2ページ
- 1
- 2
