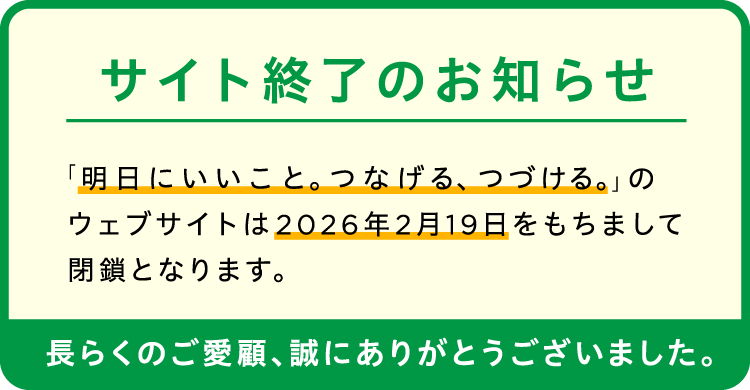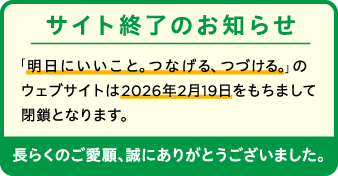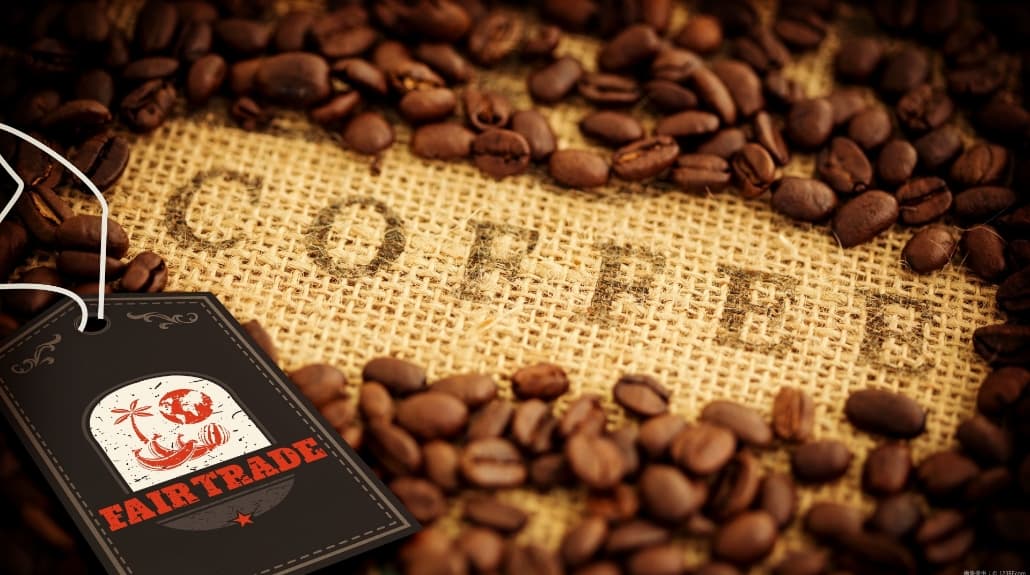
この記事でわかること
SDGsの観点から、発展途上国での貧困対策・飢餓対策などが求められています。日本で暮らす私たちが、現地で直接的に支援活動することは難しいかもしれません。しかし「フェアトレード」に関わることでなら、日常の延長線上で実施することも可能です。この記事ではフェアトレードの概要や目的、対象製品の探し方などについて紹介します。フェアトレードに貢献したいと考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
目次

「フェアトレード」とは何か?
フェアトレード(Fairtrade)は「公平・公正な貿易」のことで、とくに開発途上国と先進国の間の貿易において目指すべき姿とされています。日本をはじめとする先進国では、原料を発展途上国から輸入した商品、たとえばチョコレートやコーヒー、紅茶などが、極めて安く販売されていることも珍しくありません。先進国の消費者にとっては望ましい状況かもしれませんが、このような低価格を維持するために、生産者に正当な対価が支払われていないこともあります。
生産者の生活水準を適正な状態に引き上げ発展途上国が経済成長していくためにも、自然環境に考慮した生産体制を確立するためにも、本来なら持続可能な価格で取引しなければなりません。しかし実際には、先進国が発展途上国から廉価に輸入する状況が続いていました。
このような状態を改善するため、開発途上国由来の原料・製品を、先進国が適正価格かつ継続的に購入することが求められています。立場の弱い発展途上国の生産者・労働者を守るための貿易のしくみが「フェアトレード」であるともいえるでしょう。
ESGが注目された背景

フェアトレードによって廉価な輸入価格が引き起こす諸問題を解決する必要があると紹介しましたが、具体的には次の3点がとくに問題視されています。
- 児童労働
- 強制労働
- 労働環境
フェアトレードが必要とされる背景について、詳しく解説します。
1.児童労働
多くの発展途上国(生産国)では「児童労働」が常態化しています。児童労働とは義務教育を妨げるような労働や、18歳未満の危険かつ有害な労働のことです。UNICEF(国際連合児童基金)とILO(国際労働機関)の調査によると、児童労働に従事している子どもは全世界で1億6,000万人にものぼるとされています。
サハラ砂漠以南アフリカの児童労働問題はとくに深刻です。このエリアはカカオ豆の輸出国として知られるガーナなど、農業を主要産業とする国々が多い地域です。児童労働が発生する主たる原因は「生産者の貧困」だとされています。つまり生産者に適正対価がわたっていないために、児童労働が発生しているといえるでしょう。
2.強制労働
「強制労働」とは処罰(暴力)の脅威下に置かれた方が、自由意思に反して労働している状態を指します。ILOは1930年に「強制労働に関する条約(ILO29号条約)」を定めており、強制労働は基本的人権の侵害とされていますが、現在においても強制的に働かされている方々は存在しています。いわゆる現代奴隷です。
ILOの発表によると、2021年においても約5,000万人の現代奴隷が存在するとされています。現代奴隷のうち、強制結婚の被害者が2,200万人であり、強制労働の被害者は2,760万人です。これだけの数の現代奴隷が存在する一因には、廉価な取引を求められてしまうがために、労働者に適正な賃金を支払えない生産者が多いこともあげられるでしょう。
3.労働環境
発展途上国の劣悪な労働環境も、フェアトレードが求められる理由の一つです。アフリカ大陸をはじめ、東南アジア・南アメリカの発展途上国では、長時間労働せざるをえない方や、不安定な雇用形態を結ばざるをえない方が多数存在します。OECD(経済協力開発機構)のデータによると、2021年のOECD加盟国(先進国)の一人あたり年平均労働時間は1,716時間でしたが、発展途上国では平均労働時間が2,000時間を超えることも珍しくありません。
労働時間だけではなく、労働現場の安全管理が進まず、心身にダメージを負う方も存在します。生産物を廉価に買い叩かれてしまっては労働環境を改善する余裕も生まれないため、労働者の権利を守るためにもフェアトレードを推進することが望まれます。
フェアトレードの目的
児童労働・強制労働・劣悪な労働環境などを是正するためには、発展途上国の生産者にも適正な対価が支払われなければなりません。しかし現実的には、立場の弱い発展途上国が、先進国の事業者から不公平・不平等な貿易を強いられてしまっています。
そもそも先進国と発展途上国との間に格差が広がった一因は、奴隷制度や植民地支配の歴史に遡ります。不当な支配を受けていた国々は第二次世界大戦後に独立を果たしましたが、経済的な立場は是正されず、適正価格で取引できないケースも少なくありませんでした。安い対価しか受け取れないために児童や現代奴隷を働かせることになり、さらには労働環境が劣悪なまま放置されてしまっているのです。
このような背景を鑑み、発展途上国(生産国)と先進国との間で「公正・公平な貿易」を成立させることがフェアトレードの目的です。そして公正・公平な取引を通じて、生産国における人権問題・環境問題・貧困問題などを解決していくことが期待されています。
フェアトレードの基準
フェアトレードにまつわる国際的な法律・条約は存在しないため、市場経済的な価値観に任せて放置してしまえば、立場の弱い生産国が不利になってしまうでしょう。それではどの程度の水準で取引すれば公正・公平な貿易、つまりはフェアトレードだといえるのでしょうか。
実はフェアトレードを推進する団体は世界中に複数存在しており、それぞれフェアトレードの目安(基準)を掲げています。ここからは代表的な基準である「WFTO」「国際フェアトレード基準」について見ていきましょう。
「WFTO」による10原則
WFTO(World Fair Trade Organization|世界フェアトレード連盟)は各国のフェアトレード推進組織の連合体で、1989年に発足しました。フェアトレード団体が順守すべき指針として、次の10原則(フェアトレードの10の指針)を掲げています。
- 生産者に仕事の機会を提供する
- 事業の透明性を保つ
- 公正な取引を実践する
- 生産者に公正な対価を支払う
- 児童労働および強制労働を排除する
- 差別をせず、男女平等と結社の自由を守る
- 安全で健康的な労働条件を守る
- 生産者のキャパシティ・ビルディングを支援する
- フェアトレードを推進する
- 環境に配慮する
社会的・経済的に弱い立場に置かれてしまう小規模事業者が貧困・不安定な収入状態から脱し、経済的な自立を果たすことが一番に掲げられています。そのためには長期的な取引を確立し、生産者が健全に生活できるようにすることも目指さなければなりません。また、公正な対価とは関係者全員の合意が必要という考えに基づき、「生産者自身が公正だと考える価格」を支払うとされています。
先述した児童労働を排除し、男女平等など人権を順守することも掲げられていることが特徴です。また、経済的配慮のみならず、環境面にも配慮しサステナブルな生産体制・輸送体制に寄与することも掲げられています。
国際フェアトレード基準
「国際フェアトレード基準」は国際フェアトレードラベル機構(Fairtrade International)によって定められた基準です。この基準は基準委員会(Standards Committee)とステークホルダー(生産者や貿易業者など)によって定期的に見直されています。
開発途上国の小規模生産者・労働者のサステナブルな開発促進が目指されており、「生産者の対象地域」「生産者基準」「トレーダー(輸入・卸・製造組織)基準」「産品基準」と多岐にわたる基準が定められていることが特徴です。
たとえば生産者の対象地域は「国民一人あたり収入」「経済格差」「世界銀行ジニ係数」「人間開発指数」などを考慮して決められます。トレーダー向けの基準としては「トレーサビリティの確保」「前払いの保証」「持続的な取引の促進」などが定められており、たとえ市場相場が下落しているとしても、生産者組織にフェアトレード最低価格を保証しなければ、生産者と直接取引する輸入組織として「フェアトレード認証」受けることはできません。
さまざまな基準が存在していますが、これら基準すべてに共通しているのが、「経済」「社会」「環境」の三原則です。それぞれの原則についても紹介します。
経済的基準
経済的基準では次の要素が掲げられています。
- フェアトレード最低価格の保証
- フェアトレード・プレミアムの支払い
- 長期的な取引の促進
- 必要に応じた前払いの保証など
生産者が持続可能かつ健全に生活できるよう、取引価格のみならず、取引条件にも配慮しなければなりません。
社会的基準
社会的基準として掲げられている要素は次の4項目です。
- 安全な労働環境
- 民主的な運営
- 差別の禁止
- 児童労働・強制労働の禁止など
児童労働・強制労働を排除することはもちろん、すべての生産者・労働者の人権を守ることが重要といえるでしょう。
環境的基準
環境的基準として定められているのが次の項目です。
- 農薬・薬品の使用削減と適正使用
- 有機栽培の奨励
- 土壌・水源・生物多様性の保全
- 遺伝子組み換え品の禁止など
これら環境面にも配慮しなければ、サステナブルな生産体制は築けません。効率性だけではなく、持続可能性も重視することが求められます。
フェアトレードの対象製品

国際フェアトレード基準による「国際フェアトレード認証」の対象となっている製品は、「食品」「食品以外」の2つに大別されます。
【食品】
フェアトレード対象の食品は、発展途上国が代表的な生産地となっている次の12産品です。
| 産品名 | 代表的な製品 |
|---|---|
| コーヒー | 焙煎豆 |
| 生鮮果物 | バナナ、りんご、アボカド、ココナッツ、レモン、オレンジ、ワイングレープ |
| カカオ | チョコレート |
| スパイス・ハーブ | スパイス:バニラ、クミン、コショウ、ショウガ、シナモンなど ハーブ・ハーブティー:ルイボス、ハイビスカス、カモミールなど |
| 蜂蜜 | 蜂蜜 |
| ナッツ | カシューナッツ、胡桃、アーモンド、マカデミアンナッツ |
| オイルシード・油性果実 | ごま、オリーブ、大豆など |
| 加工果物・野菜 | ドライフルーツ、フルーツジュース、ドライ野菜 |
| サトウキビ糖 | 砂糖 |
| 茶 | 紅茶、緑茶など |
| 野菜 | ピーマン、メロン、ジャガイモ、ひよこ豆、レンズ豆など |
| 穀類 | 米、キヌアなど |
【食品以外】
食品以外の製品としては、次の4産品がフェアトレード対象です。
| 産品名 | 代表的な製品 |
|---|---|
| 繊維 | コットン |
| 花 | バラ、カーネーションなど |
| スポーツボール | サッカーボール、フットサルボールなど |
| 金 | 金 |
フェアトレード認証ラベルについて
記事内でも少し触れましたが、フェアトレード商品であることを示す証明として「フェアトレード認証ラベル」が各機関から付与されます。認証ラベルは次の3種類に大別されます。
- 国際フェアトレード・ラベル機構(FLO)
- 世界フェアトレード機関(WFTO)
- 団体独自のフェアトレード認証ラベル
それぞれの認証ラベルの特徴について見ていきましょう。
国際フェアトレード・ラベル機構(FLO)
1990年代になると、フェアトレード・ラベルの仕組みが多くの先進国に広がりました。このような状況で、フェアトレード基準・ラベルを統一するために誕生したのが「国際フェアトレード・ラベル機構(FLO)」です。
FLOができたことでフェアトレードに参入する企業の数が増えていき、フェアトレード市場も大きくなりました。現在、国際フェアトレード認証ラベル (The FAIRTRADE Marks)はフェアトレードスキームの象徴として世界中で知られています。
標準的な国際フェアトレード認証ラベルが付与されている商品は、原料生産・輸出入・加工・製造工程に至るまで国際フェアトレード基準が守られていることが特徴です。さらに農場から認証製品として出荷されるまでの過程を完全に追跡できる「物理的トレーサビリティ」が適用されています。
なお、矢印がついている国際フェアトレード認証ラベルは、チョコレート・シリアルなど非認証原料を含む製品に使用されています。パッケージ裏面で認証原料・調達方法が記載されているため、消費者が内容を確認できるようになっているのです。また、一部原料のみがフェアトレード対象である場合は、その産品名が明記された国際フェアトレード認証ラベルが用いられることも覚えておきましょう。
世界フェアトレード機関(WFTO)
FLOによって広がりを見せたフェアトレードですが、実はその後、さまざまなフェアトレード認証システムが乱立し、消費者が混乱する事態が生じました。また、原材料・製法がシンプルな製品ならフェアトレード基準を作りやすいものの、手工芸品・衣服などは基準を設けづらいという課題があったことも事実です。
このような状況で独自のフェアトレード認証を立ち上げたのが、記事前半でも紹介したWFTOでした。WFTOは手工芸品・衣服の生産者団体、それら製品を扱う先進国のフェアトレード団体で構成されていたため、複雑なフェアトレード基準を作成することができたのです。2014年から本格的な運用が始まっており、「WFTO認証ラベル製品」が市場に出回ることで、手工芸品・衣服の生産者たちにも恩恵が波及し始めています。
団体独自のフェアトレード認証ラベル
フェアトレードを管掌する世界的な法律はないため、任意の団体独自でフェアトレード認証ラベルを作ることも可能です。日本企業はFLO・WFTOが普及する以前から現地生産者と直接取引していたため、FLO・WFTOよりも厳しい基準を設け、独自に生産者と取引している企業も少なくありません。
フェアトレードに関する取り組み
ここからはフェアトレードに貢献できる取り組みを、企業側・消費者側それぞれの視点から紹介します。
企業側ができる取り組み
企業としてはサプライチェーン全体を見直し、仕入先をフェアトレードの観点から見直してもいいでしょう。発展途上国の生産者に対する対価を見直すことも考えられます。さらに一歩踏み込んだ取り組みとしては自社商品の「フェアトレード認証」取得を目指すこともおすすめです。
消費者側ができる取り組み
一人の消費者としても、フェアトレードに貢献することは可能です。たとえばフェアトレード認証を受けた製品を積極的に購入すれば、企業にフェアトレードを促せるでしょう。また、フェアトレードに関するイベントやカンファレンスに参加し、実際にフェアトレードを推進する取り組みに関わってみることもおすすめです。
フェアトレードの問題点と課題
フェアトレードにはさまざまなメリットがありますが、現実的には問題・課題も少なくありません。代表的な問題点は次のとおりです。
- 知識と行動の乖離
- 曖昧なフェアトレード基準
- SDGsウォッシュ
それぞれ詳しく解説します。
知識と行動の乖離
フェアトレードを「知っている」としても、実際にフェアトレード商品を「購入する」までに至らない方も多いです。他の商品よりも高いフェアトレード商品を買うことに抵抗を覚えるのも自然なことでしょう。しかしフェアトレードとして生産者に適正な対価が支払われている以上、消費者としても適正な対価を負担する必要があります。よりフェアトレードを推進するために、まずは誕生日プレゼントや記念日の贈り物など、少し高価な商品を購入するタイミングからフェアトレード商品を試してみてもいいかもしれません。
曖昧なフェアトレード基準
この記事で紹介したとおり、フェアトレードの基準は必ずしも明確になっているわけではありません。各国の団体・組織によって基準がバラバラであるため、「フェアトレード」とラベリングされている商品であっても、生産者にどのくらい適正対価が支払われているか不透明な状況です。フェアトレードに貢献するためには、信頼できるフェアトレード認証ラベルを見極める必要があります。
SDGsウォッシュ
商品を売ることに主眼を置いた企業が、実態が伴っていない商品をサステナブル商品だとして販売するケースも散見されます。いわゆる「SDGsウォッシュ」「グリーンウォッシュ」です。このような消費者を騙すような行為は、欧米では規制対象となりつつあります。しかしフェアトレードへの意識が消費者間で広がるほど、実態と無関係にフェアトレードを謳う企業が現れる可能性もゼロではありません。フェアトレードを適正に推進していくために、企業・消費者の双方がフェイク情報に騙されないよう注意する必要があるでしょう。
まとめ
地球全体としてサステナブルに発展していくためには、先進国のみならず、発展途上国にも適正な対価が支払われなければなりません。人権を順守し、環境を守るためにも、今後ますますフェアトレードを推進していく必要があるでしょう。
しかしフェアトレードを進めるためには、消費者が負担する小売価格が今より増えることも事実です。いきなり利用するすべての商品をフェアトレード商品に置き換えることは難しいかもしれませんが、一人ひとりが可能な範囲で取り組んでみてください。