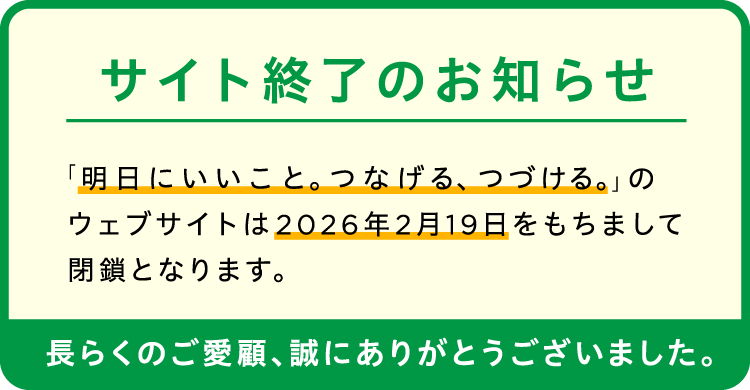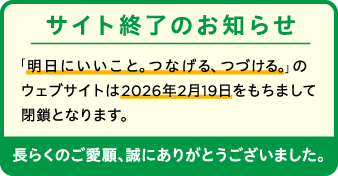この記事でわかること
サーキュラーエコノミーとは、日本を含む世界各国で推進されている経済システムのことで、深刻化している環境問題や資源不足といった課題解決に貢献できると期待されています。この記事ではサーキュラーエコノミーについての概要や必要とされる理由、導入するメリットについて解説します。
目次

サーキュラーエコノミーって何?
環境汚染や気候変動などの問題によって、エコな取り組みに対する意識が高まっています。環境問題を解決する手段の一つとされる「サーキュラーエコノミー」について、詳しく解説します。
廃棄物を限りなくゼロにする経済システムづくりのこと
サーキュラーエコノミー(Circular Economy)とは、日本語に置き換えると「循環型経済」を意味します。資源や素材を長期的に保全・維持し、廃棄しないことを前提とした製品開発や生産を行い循環させる経済システムのことです。
従来の経済システムでは、大量生産・大量消費が一般的であり、結果的に大量廃棄につながっていました。このような経済システムを「リニアエコノミー(線型経済)」と呼びますが、サーキュラーエコノミーでは、リニアエコノミーの「使った商品はゴミとして捨てる」という考えを一新した経済システムです。
資源や消費エネルギーの削減、廃棄物を最小化することによる環境負荷を軽減するとともに、製品に新たな価値を与えて経済成長につなげる目的もあります。
サーキュラーエコノミーと「3R」との違い
Reduce(リデュース)・Reuse(リユース)・Recycle(リサイクル)の「3R」は、地球環境に優しいエコな活動として、これまでも取り組まれてきました。
- Reduce(リデュース):資源の使用量や廃棄物の発生を抑える取り組み
- Reuse(リユース):使用した製品や製品のパーツなどを繰り返し使用する取り組み
- Recycle(リサイクル):廃棄物などを再資源化し再び利用する取り組み
3Rは廃棄物を最小限に抑える設計や、再利用・再資源化する取り組みですが、廃棄物がゼロに抑えられるわけではありません。一方、サーキュラーエコノミーは廃棄物をゼロにすることが前提であり、開発・生産・使用のサイクル全体を通して、資源の循環可能なシステムを構築する取り組みです。
サーキュラーエコノミーが必要とされる背景と理由
サーキュラーエコノミーは環境問題や資源の枯渇、またそれらの問題を解決しようとする社会の意識向上などの理由から必要性が高まっています。

資源不足への対応
サーキュラーエコノミーは、資源不足の問題を解決できると期待されています。現代の産業では石油や石炭、天然ガスなどの化石燃料に頼っている状況です。しかし、これらの化石燃料は地球上に限られた量しか存在せず、将来的に資源が枯渇することが懸念されています。
また近年、人口の増加や新興国の発展にともない、資源不足の問題は早まるとも考えられています。
このような理由から、資源の需要が高まると安定的な供給が難しくなり、価格の高騰や資源を巡った国家間の争いといったリスクに発展する可能性もあります。
そのため、資源を効率的に活用する取り組みであるサーキュラーエコノミーが必要とされています。有限な資源を効率的に使用する方法を考え、永続的に使用できる自然エネルギーを利用した再生可能エネルギーの活用を目指す必要があります。
地球の環境保護や脱炭素化の実現
サーキュラーエコノミーはゴミを出さない取り組みであるため、地球環境の保護や二酸化炭素(CO2)排出量を実質ゼロにする、脱炭素化につながることも必要とされる理由のひとつです。
大量の廃棄物や工業・生活排水、大気汚染などによる自然環境への負荷が社会問題となっています。とくに大きく環境負荷を与えて深刻化しているのは、プラスチックゴミが海洋に蓄積する海洋汚染や、温室効果ガスの排出量増加による地球温暖化といった問題です。これらの問題は異常気象や生態系の変化などにつながり、いずれは人間を含めすべての生物に悪影響をおよぼすとされています。
サーキュラーエコノミーはプラスチックを含めゴミの排出量を削減し、長期的に使用できる、あるいは再利用の拡大が必要となる取り組みです。ゴミの排出量を削減できることで廃棄する際のCO2削減も可能となり、環境保護や脱炭素化にも貢献します。
ESG投資の活発化
サーキュラーエコノミーに取り組んでいる企業は、投資も受けやすいといった理由も関係しています。企業が安定して長期的に成長を続けるには、ESG(環境・社会・企業統治)が影響するという考えが浸透しています。投資家が売上だけではなく、ESGを重要な判断材料とするESG投資が世界の動向です。
【ESG】
-
環境(Environment)
地球の自然環境の保護、環境破壊の防止・改善への配慮
-
社会(Social)
働き方の改善、地域貢献などの社会活動、製品の品質や安全につながる取り組み
-
企業統治(Governance)
経営体制の構築、法令遵守やリスク回避、情報開示など経営の透明性を意識
SDGsの達成に向けて
持続可能な開発目標であるSDGs(Sustainable Development Goals)では、地球の環境問題や貧困、格差といった問題をなくし、公平で平和な社会と持続可能な発展を目指しています。17のゴール(目標)が掲げられ、2030年までに問題解決や改善、達成することを目標に世界共通の認識で取り組まれています。
サーキュラーエコノミーの実現は、さまざまな環境問題を解決できる手段でもあります。とくに、SDGsの以下の目標に貢献すると期待されています。
【関連性の高いSDGs】
- 12.つくる責任 つかう責任
- 13.気候変動に具体的な対策を
- 14.海の豊かさを守ろう
- 15.陸の豊かさも守ろう
サーキュラーエコノミーの3原則について
サーキュラーエコノミーの国際的な推進機関であるエレンマッカーサー財団は、サーキュラーエコノミーの原則を以下のように3つ掲げています。
自然システムの再生
有限な資源の使用を避け、再生可能資源を活用するなどして自然環境に配慮することです。
材料の採取、製造、廃棄のリニアエコノミーから転換することで、自然のプロセスをサポートし、自然が本来持っているシステムによる再生を図ります。
製品、素材を循環
長く使用できるように製品や部品、素材の耐久性を高め、使用した後もリユースやリサイクルを促進します。部品や原材料を繰り返し使用し続けることで、無駄になるものが何もなく製品と材料の価値を維持します。
廃棄物、汚染をなくす
原材料の採取、製造、消費のすべての工程で廃棄物や汚染が出ないような設計を前提とし、経済活動による環境や健康への負荷を低減します。
サーキュラーエコノミーのメリット
環境問題や社会の動向などをふまえると、サーキュラーエコノミーは行うべき活動です。そしてサーキュラーエコノミーに取り組むことで、さまざまなメリットや効果につながります。
中長期的な資源確保、資源コストが抑えられる
サーキュラーエコノミーは、資源の確保やコスト削減につながります。生産のプロセスでは、資源やエネルギー消費の使用量を低減でき、使用ずみの製品は再利用やリサイクルなどを行って、繰り返し資源として活用できます。自然の資源を節約することにつながり、資源の採取や運搬に関連するコストも抑えられるでしょう。
性能や耐久性を向上させることで製品の寿命が延び、消費者にとっても購入コストの低減が期待できます。これまで廃棄処理のために必要だったコストや、CO2排出量なども同時に抑えられるため、社会全体を通してメリットにつながります。
新たなサービスやビジネスの創出につながる
サーキュラーエコノミーは、大量生産・大量消費・大量廃棄を前提とするリニアエコノミーとは異なる経済システムです。そのため、実現に向けてさまざまな工夫や施策が求められ、新たなサービスやビジネス創出の可能性を秘めています。
高度な技術やテクノロジー、新たな分野でのノウハウも必要になることから、新たなビジネスパートナーとの連携や市場の開拓にもつながり、あらゆる方向に発展する可能性があります。
サーキュラーエコノミーを構築した事業は、ESG投資やSDGsへの関心から投資家や消費者からのニーズも高まっています。今後サーキュラーエコノミーの経済効果も高まると予測されているため、取り組むことは企業にとって大きなメリットがあるといえるでしょう。
SDGsの実現に向けた手段となる
SDGsは、課題解決に向けてすべての人が取り組むべき目標です。とくに企業活動は多くの人や社会、経済に大きな影響を与えるため、積極的に取り組んでいく責任があります。また、顧客や取引先、投資家などあらゆるステークホルダーから信頼され、企業価値を高めるためにもSDGsの取り組みは必要不可欠です。
上述したようにSDGsにはサーキュラーエコノミーの取り組みにより、課題の改善や解決、目標達成につながるものもあります。サーキュラーエコノミーに取り組むことが同時に、SDGsの実現に向けた手段にもなるといったメリットは大きいでしょう。
企業イメージの向上につながる
サーキュラーエコノミーに取り組むことで、企業イメージの向上につながるメリットもあります。若い世代の方たちは環境に配慮していることに高い関心を持っているため、市場での優位性が高まります。
また、リクルートの面でも優位になりやすく、優秀な人材確保につながります。反対に、環境活動につながる取り組みをしていない場合は取引しないといった企業もあります。企業イメージの向上により、さまざまメリットを得られます。
サーキュラーエコノミーのデメリット
サーキュラーエコノミーは取り組むべきものですが、デメリットな面もあります。
開発に多額のコストがかかる
リサイクルや再資源化するシステムや技術を構築する必要があるため、開発に関わる人件費や設備の導入費などの大きなコストがかかります。また、これまでの生産工程を変更し、リサイクルや再資源化のための運用コストも必要です。
しかし、中長期的な目線ではメリットの部分でも紹介したとおり、原材料の取得にかかるコストを抑えられます。ステークホルダーへのアピールにもつながるため、コストのデメリットは解消されると考えられます。
高度な技術が必要となる
サーキュラーエコノミーを実現するには、高度な技術が必要です。素材を分解して再利用するための技術ももちろん困難ですが、長く使用を続けてもらえるように耐久性を向上させる開発や、長期的に愛用してもらえるような工夫も必要です。ニーズの移り変わりが早い現代においては、消費者の満足度も考慮しなければなりません。
従来のリニアエコノミーの経済システムは廃棄するだけでしたが、サーキュラーエコノミー実現に向けて技術力の向上が求められています。
製品開発の制約が生まれやすい
サーキュラーエコノミーでは、製品開発の制約が生じる可能性がある点がデメリットです。リサイクルや再資源化を前提として開発やデザインを行うため、製品のパーツを分解しやすくする、素材の使用を限定するなどの必要があるためです。
たとえば、衣類の場合は耐久性や機能性を持たせるため、ポリエステルなどの素材を混合する素材が開発されています。天然由来のシルクや綿と比べると日常生活では便利な素材ですが、混合素材を再資源化するために高度な技術が必要です。
このようにリサイクルや再資源化を前提とすると、選択肢が限られたり打開策が必要になったりするため簡単には進められない可能性があります。
サーキュラーエコノミーに対する日本政府の取り組み
世界的に推進されているサーキュラーエコノミーですが、日本でも政府主導で計画や目標を定めてサーキュラーエコノミーへの転換を図っています。
環境省「第四次循環型社会形成推進基本計画」
日本では循環型社会を目指し、2000年に循環型社会形成推進基本法が公布されています。この法律は廃棄物の発生を抑制し、資源を循環させる仕組みをつくり環境への負荷を最小限に抑えるためのものです。
また、政府が「循環型社会形成推進基本計画」を策定し、5年ごとに見直すことが必要とされています。2018年には、「第四次循環型社会形成推進基本計画」が閣議決定されています。第四次循環型社会形成推進基本計画では以下の新たな計画を掲げ、国が対策すべき施策を示しています。
- 地域循環共生圏形成による地域活性化
- ライフサイクル全体での徹底的な資源循環
- 適正処理の更なる推進と環境再生 など
また、2024年6月時点では第五次循環型社会形成推進基本計画が進められています。
経済産業省「循環経済ビジョン2020」
2020年には経済産業省がサーキュラーエコノミーへの転換に向けて、今後日本が進むべき方向性を示した「循環経済ビジョン2020」を公表しています。
従来の3Rの延長ではなく、経営戦略・事業戦略に位置づけた循環性の高いビジネスモデルの創出や、市場や社会から適正な評価を受けるためにも積極的に取り組み説明責任を果たす必要があるといった内容があげられています。
サーキュラーエコノミーの企業の取り組み事例
サーキュラーエコノミーに対する日本政府の動向により、多くの企業でも取り組みが進められています。
不要になった服の回収、再生プロジェクト
サーキュラーエコノミーは、ファッション業界でも取り組まれています。販売して不要になった自社の衣服を消費者から回収し、再び新たな服をつくる循環型の取り組みを実施している企業があります。服を捨てずに店舗に持っていくことで、消費者も環境活動や社会に貢献できる取り組みです。
同社ではこのほか回収した衣服を必要としている方へ送るリユースの取り組みや、商品のライフサイクルで廃棄物やCO2排出量、資源の使用量を削減するリデュースの取り組みも行っています。
PETボトル製品を100%サスティナブル素材へ切り替え
ペットボトル飲料は外出先での水分補給など生活に欠かせないものですが、環境問題にもつながる要素のひとつです。
大手飲料メーカーでは、ペットボトル素材を100%サスティナブルな素材へと切り替える取り組みを行っています。リサイクルペットボトルや植物由来のペットボトルを含め、100%サスティナブル素材を目指しています。
同社ではペットボトルのラベルをなくしたラベルレス製品の販売や、販売した同等の飲料容器の回収などの活動も行っています。
リデュース、リユース、リサイクルや再生可能資源の拡充
私たちの移動に必要な車やバス、航空機にも使用される車両製品はさまざまな部品から成り立っています。大手車両部品メーカーではサーキュラーエコノミー貢献のため、リデュース、リユース、リサイクルや再生可能資源の拡充に向けてさまざまな取り組みを行っています。
部品の軽量化や耐久性向上の技術開発、資材の使用量を削減する取り組み、車用品のリペアや自動車のシェアサービスなどを行っています。多様な取り組みを展開し、サーキュラーエコノミーへの貢献とビジネスモデルの創出も成功させています。
再生プラスチックを使用したパッケージの採用
シャンプーや洗剤など日用品に使われる容器類は、生活の中にあふれています。この容器パッケージの資源循環を目指し、再生プラスチックを使用したパッケージを採用する企業もあります。さらに、ペットボトルをリサイクルした素材でのパッケージ展開も行っています。
また消費者にも促進するため、リサイクル活動に協力した消費者にポイントを付与する取り組みや、日用品を量り売りする販売方法なども取り入れ、サーキュラーエコノミーを推進しています。
まとめ|ビジネスチャンスにもつながるサーキュラーエコノミー
サーキュラーエコノミーは新たな事業展開やビジネスモデルの創出、企業イメージ向上など多くの効果につながる取り組みです。高度な技術や多額なコストが必要といった懸念する部分もありますが、取り組まなければ市場での競争に勝てず、ステークホルダーから評価されないという事態につながる恐れもあります。ビジネスチャンスであるととらえて、企業事例も参考に取り組んでいきましょう。